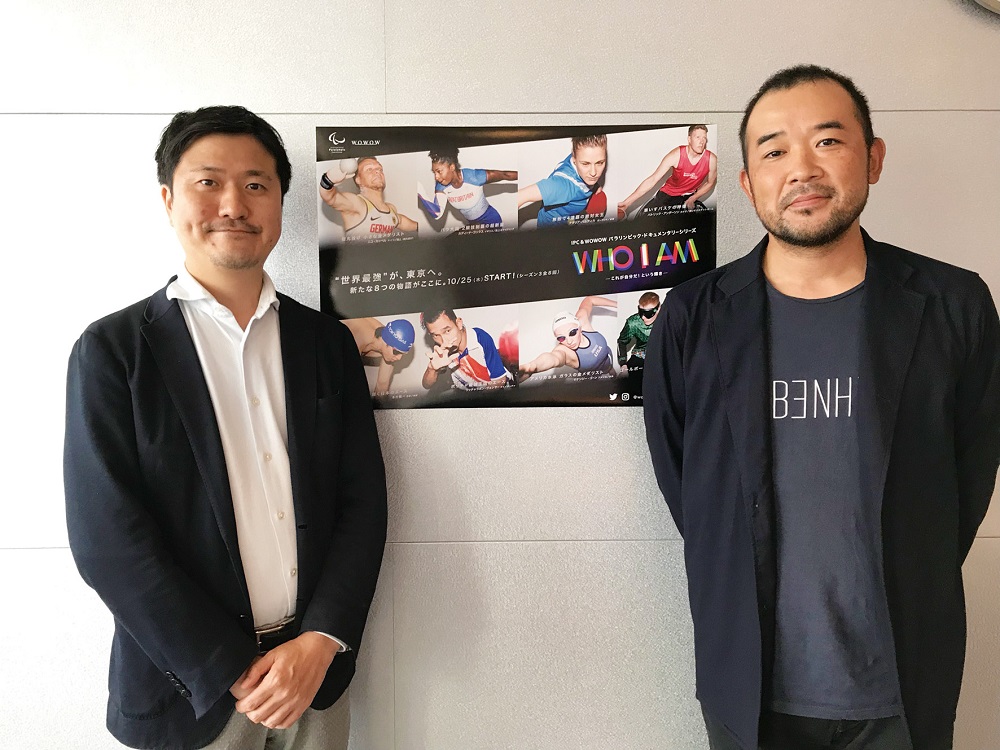
自分自身に問いかける「WHO I AM」(太田慎也さん)
「W H O I A M」は、2016年にスタートし、今年で3シーズン目。番組立ち上げから制作に携わってきた太田慎也さんは、WOWOW世代。中学生の時には世界のスポーツに夢中になっていた。だから、同志社大学を卒業すると、WOWOW第一志望で就職した。
2013年に東京オリンピック・パラリンピック開催が決定し、社をあげて何ができるかを議論していた時に持ち上がったのが、パラリンピックのスーパースターをドキュメンタリーで描くこと。そのプロデューサーとして太田さんが抜擢されたのだった。
「当時、パラリンピックはおろか、障がい者に接することもなかった。だから会社から打診された時に、ものすごく微妙な顔をしたと思いますよ」
番組準備のため、2015年に初めて訪れた水泳の世界選手権で、衝撃を受けた。
「選手たちが義足を放り投げるようにして、プールに飛び込んでいる。着用しているジャージには、国旗が縫い付けられていた。これはまさしく世界最高峰の舞台なんだって」
目を引いたのは、ブラジルのダニエル・ディアス。レースが終わるとメディアが一斉に彼の元に駆け寄り、コメントを求めた。
「テニスのロジャー・フェデラーと変わらない。世界的なスターだと実感しました」
上肢・下肢に障がいがあるディアスの笑顔は、キラキラ輝いていた。オレは、彼のように輝いているか。パラアスリートを間近に見て、自問自答した。
「シリーズタイトルを議論している時、英語が堪能な後輩プロデューサーが、選手に〝This is WHO I AM(これが自分だ)〞と宣言させたい、と。それで決まりました」
初めてダニエルに挨拶をした時に、握手しようと右手を出して思わず引っ込めてしまった。
「ダニエルの腕が短いことで、反射的に〝いけない〞と。今なら、短い腕を両手でつかんで握手する。でも、あの時躊躇した自分がいた。それは日本に暮らす多くの人の、ある意味偽らざる姿だと思ったんです」
それを、この番組で変えていこう。ディアスが出発点だった。
番組制作で重視しているのは、障がいをことさら強調しないこと。選手たちが、いかに自分と向き合い、人生やスポーツを楽しんで世界の頂点を目指しているか。そこにこそ、フォーカスしたい。
「シーズン1は、8人の選手のロード・トゥ・リオ。生い立ちからスポーツとの出会い、そしてリオに向かって何に取り組んでいるかを、王道のスタイルで作りました」
難しかったのは、シーズン2。パラリンピックの翌年で、選手たちはそれぞれ故郷に戻り
リラックスしている。アスリートとして最前線を突っ走っている時期ではない。
「でも、だからこそ、彼らの真の生き様に迫れたと思う」
国際パラリンピック委員会(IPC)との共同プロジェクトであったことは、選手へのアプローチを後押ししてくれた。それでも難航したものもある。
「ボスニア・ヘルツェゴヴィナのシッティングバレーボール選手、サフェト・アリバシッチには、ボスニアのパラリンピック委員会経由でようやく教えてもらった連絡先に電話をかけたら本人の携帯で、英語が通じない。ジャパン、テレビくらいはかろうじて理解してくれました」
ボスニアに詳しい専門家に相談し、連絡する道筋を見つけて実現にこじつけた。
取材するうえで心がけているのは、選手との距離感だ。探りながら、かつ懐に飛び込まなければ、番組は完成しない。
「じっくり、選手と一緒に番組を作っていく感覚ですね」
2020年東京パラリンピック開催までの5シーズン、計40人のトップアスリートに迫る。W O W O W は有料放送だが、「WHO I AM」の過去のシーズンは簡単な登録だけで無料で視聴できる。
「作って終わりじゃない。ここが始まりだと思っています。一人でも多くの人にパラリンピックの、パラアスリートの素晴らしさを知ってもらいたい。それは、この番組を製作する者のミッションだと思っています」



取材・文/宮崎 恵理
写真/WOWOW・編集部